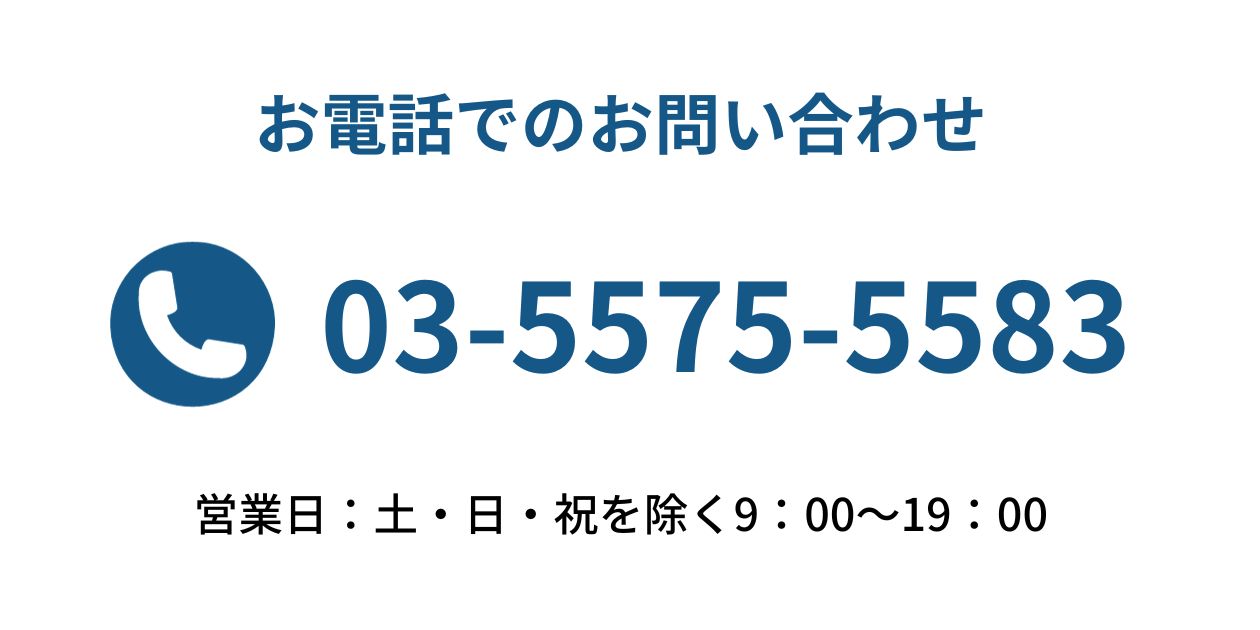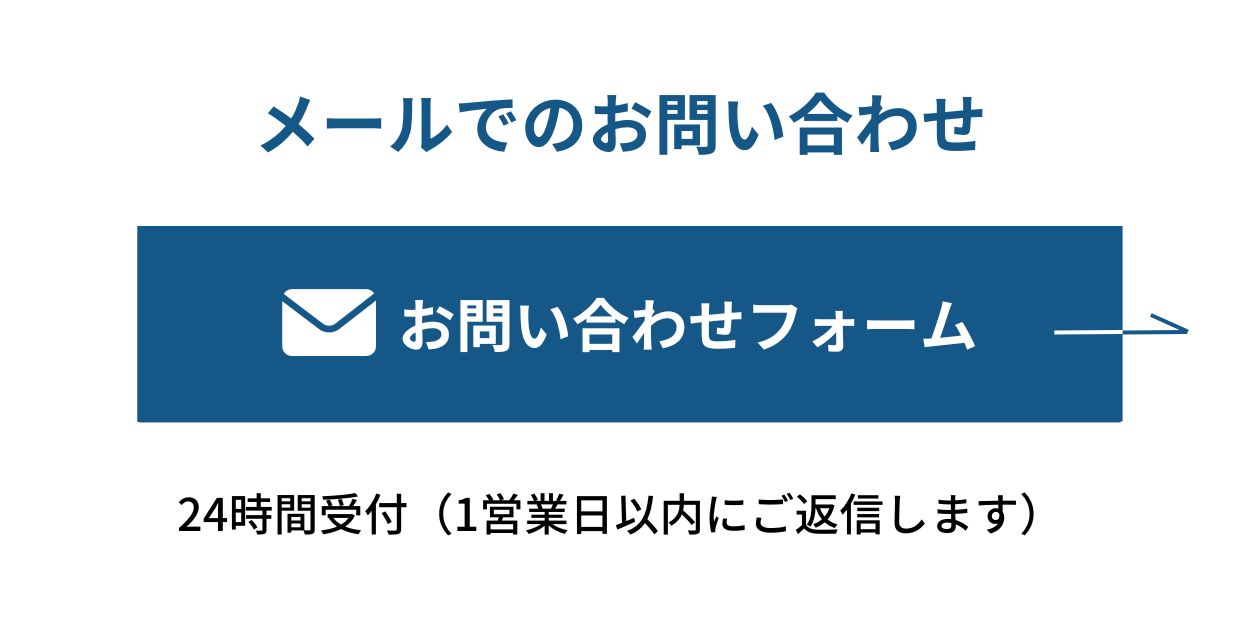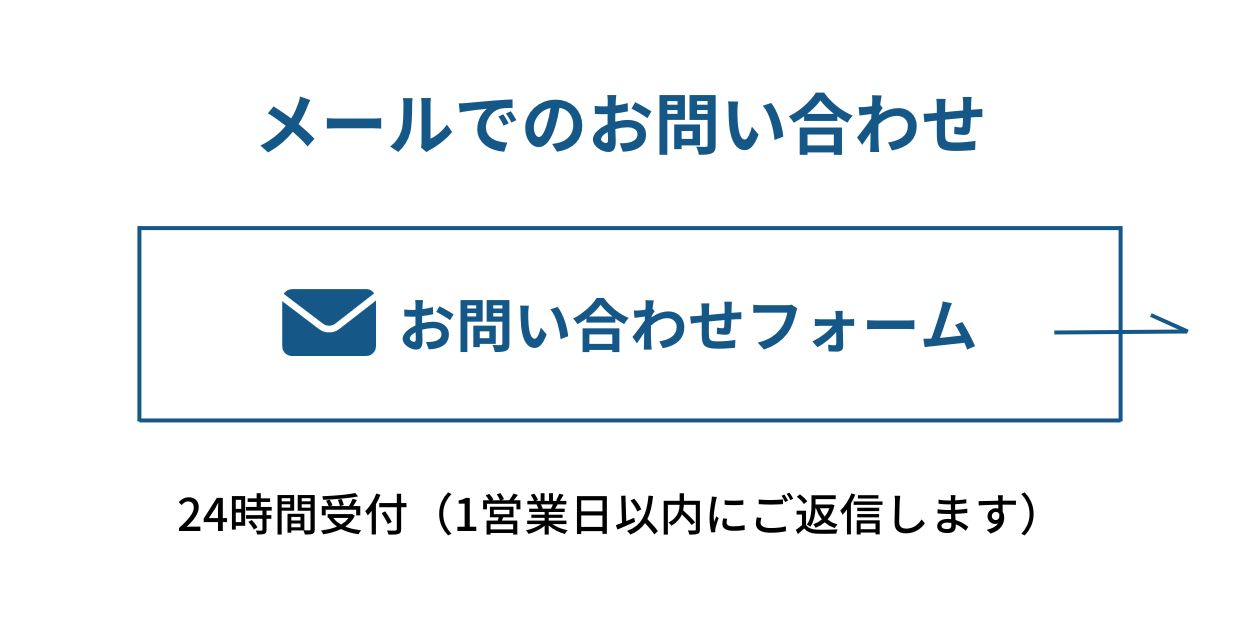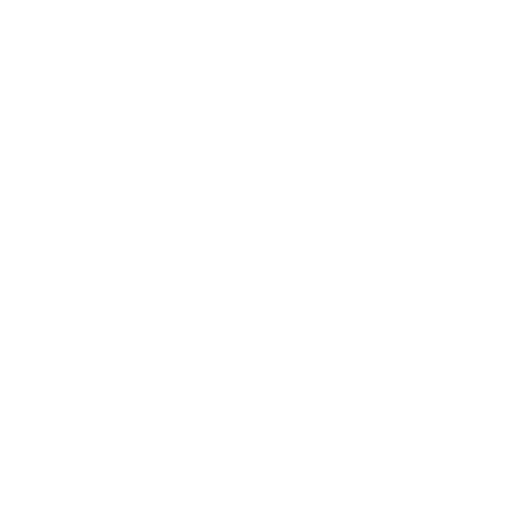- Call From Japan
- 03-5575-5583
- Email(24時間OK)
- info@tanishima.biz
難民認定申請
※以下は、基本的に外務省と法務省の資料に基づいて作成しました。UNHCR等は異なる解釈を採っている可能性があります。
1.概要
日本は、1981年6月の通常国会において、「難民の地位に関する条約」(難民条約)及び「難民の地位に関する議定書」(議定書)への加入が承認され、1981年10月3日に難民条約に、1982年1月1日に議定書に加入、1982年1月1日から難民条約・議定書が発効しました。
それに伴い、難民条約・議定書の諸規定を国内で実施するため、難民認定制度が整備されました。この制度では、難民である外国人は、難民認定申請を行い、法務大臣から難民であるとの認定を受けることができ、また、難民条約に規定する難民(条約難民)としての保護を受けることができます。
「難民」とは、難民条約1条又は議定書1条の規定により定義される難民を意味し、それは、「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」とされています。
難民認定手続とは、外国人がこの難民の地位に該当するかどうかを審査し決定する手続です。
2.難民の定義
(1)はじめ
難民条約1条A⑵だけが適用されます。その結果、以下の定義になります。
「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を望まないもの及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの」
この難民の要件を抽出すると、以下のようになります。
(a)人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に、迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有すること
(b)国籍国の外にいる者であること
(c)その国籍国の保護を受けることができない、又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者であること
(2)難民条約1条A⑵の「難民」の定義
日本は難民条約加入に当たって、1条B(1)の地理的制限を付さないことを宣言し、また議定書にも加入しましたので、難民について時間的制限(1条A(2)下線部の部分 )も地理的制限もなく適用することになります。
難民条約1条A⑴は、従前の国際協定により認められた難民のカテゴリーを記載し、現在日本で適用が問題になることは考えられません。A⑵(下線部 を除く)だけが適用されます。
(難民条約)
|
第1章 一般規定 第1条【「難民」の定義】 A (2) 1951年1月1日前に生じた事件の結果として、かつ、人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を望まないもの及びこれらの事件の結果として常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、当該常居所を有していた国に帰ることができないもの又はそのような恐怖を有するために当該常居所を有していた国に帰ることを望まないもの。 ~第二文略~ |
(3)主張・立証責任
入管法61条の2第1項等の規定に照らし、原告において主張・立証する必要があります。
民事訴訟における「証明」とは、裁判官が事実の存否について確信を得た状態をいい、合理的な疑いを容れることができないほど高度の蓋然性があるものでなければならず、通常人なら誰でも疑いを差し挟まない程度に真実らしいとの確信が必要です。
その理由は、民事訴訟における事実の証明の程度は、特別の定めがないにもかかわらず、軽減することは許されないところ、難民条約及び難民議定書には難民認定に関する立証責任や立証の程度についての規定は設けられておらず、入管法等にも立証責任を緩和する規定は存在しないから。
(4)「迫害」
「迫害」とは、通常人において受忍し得ない苦痛をもたらす攻撃ないし圧迫であって、生命、身体又は身体の自由の侵害又は抑圧及びその他の人権の重大な侵害を指します。具体的には殺害、不当な拘禁、不当に重い刑罰のほか、生活手段の剥奪その他様々な形態が考えられます。個々のケースに即して判断することになります。
(5)「十分に理由のある恐怖」
本人が迫害を受けるおそれがあるという恐怖を抱いているという主観的事情のみならず、通常人が当該人の立場に置かれた場合にも迫害の恐怖を抱くような客観的事情が存在していることを意味します。
(6)「社会的集団」
同様の社会的背景、習慣、社会的地位等を有して、更に一定の結合関係があり、同一の集団に属しているとの共通の意識を持つ人々のことを指します。
具体的には、特定の人種的、血縁的、政治的又は宗教的な団体、組合、会社等が該当します。
(7)「国籍国の保護」
国籍国の外交的・領事的な保護など国家機関の何らかの保護又は援助を意味しています。
具体的には、身体や財産の保護などについて、その者の属する国の大使館や領事館の援助を受けること、あるいは大使館や領事館で旅券や各種証明書などの発給、有効期間の延長の手続きを受けることなどが該当します。
(8)「国籍国の保護を受けることができない」
国籍国が保護を拒絶している場合を指します。
3.申請手続き(法務省ホームページより)
(1)入管法の条文
|
(定義) 第2条 出入国管理及び難民認定法及びこれに基づく命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 3の2 難民 難民の地位に関する条約(以下「難民条約」という。)第1条の規定又は難民の地位に関する議定書第1条の規定により難民条約の適用を受ける難民をいう。 (難民の認定) |
(2)申請期間
難民認定申請の期間について制限する規定はありません。
(3)申請窓口
難民認定申請は、申請者の住所又は現在地を管轄する地方出入国在留管理局、支局及び出張所で行うことができます。
申請は、申請者本人が自ら出頭して行ってください。ただし、申請者が16歳未満である場合や病気その他の理由により自ら出頭できない場合は、父母、配偶者、子又は親族がその者に代わって申請を行うことができます。
(4)必要書類
①難民認定申請書(各国語版)・・・1通
日本産業規格A列4番の紙に印刷してお使いになれます。
②写真(縦4cm×横3cm)・・・2葉(ただし在留資格未取者については3葉)
※ 提出の日前3か月以内に撮影された縦4cm×横3cmの無帽、正面上半身のもので、裏面に氏名が記載されているもの
③申請者が難民であることを証明する資料(又は難民であることを主張する陳述書)・・・1通
④以下の書類の提示が必要になります。
a.旅券又は在留資格証明書 (旅券又は在留資格証明書が提示できない外国人はその理由を記載した書面1通を提出してください。)
b.在留カード(在留カードを所持している場合)
c.仮上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可、遭難による上陸の許可又は一時庇護のための上陸許可を受けている外国人はその許可書
d.仮放免中の外国人は、仮放免許可書
(5)立証
難民の認定は、申請者から提出された資料に基づいて行われます。したがって、申請者は、難民であることの証拠又は関係者の証言により自ら立証することが求められます。
なお、申請者の提出した資料のみでは十分な立証が得られない場合には、難民調査官が公務所等に照会するなどして、申請者の申し立てる事実の有無について調査し、難民の認定が適正に行われるように努めます。