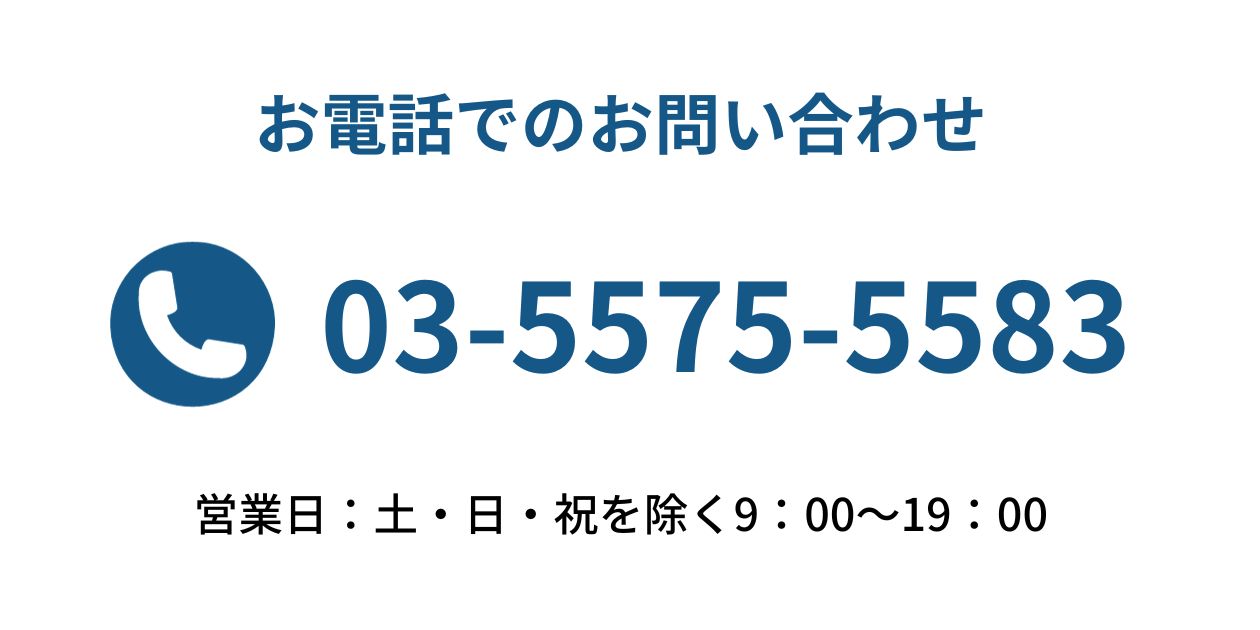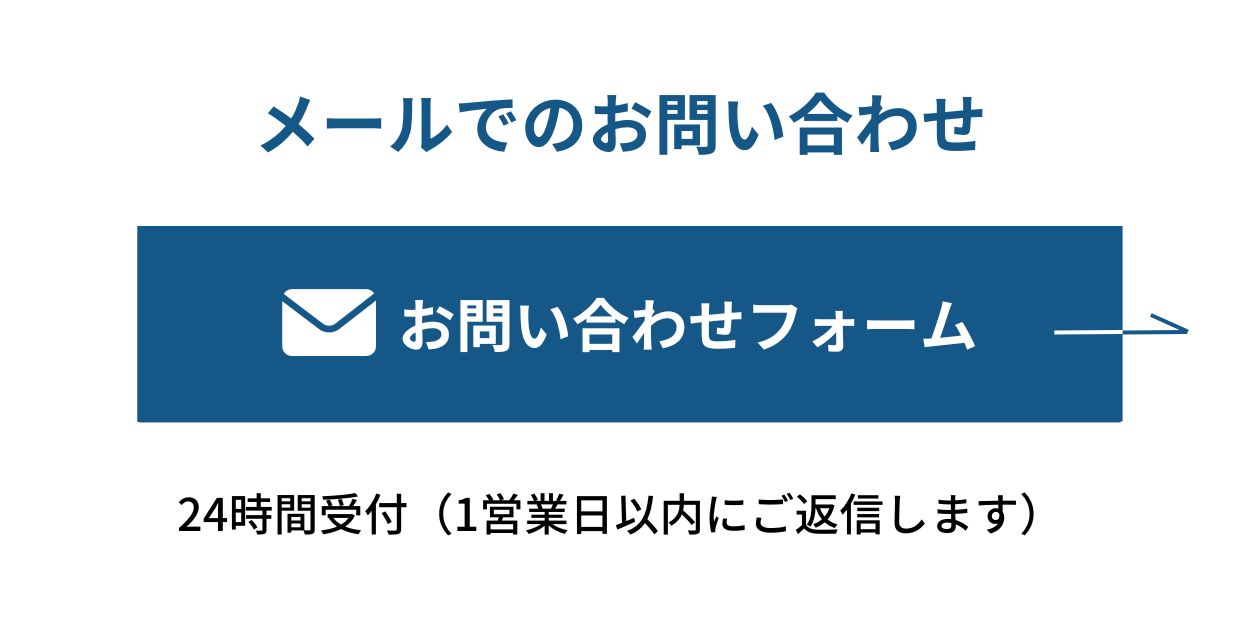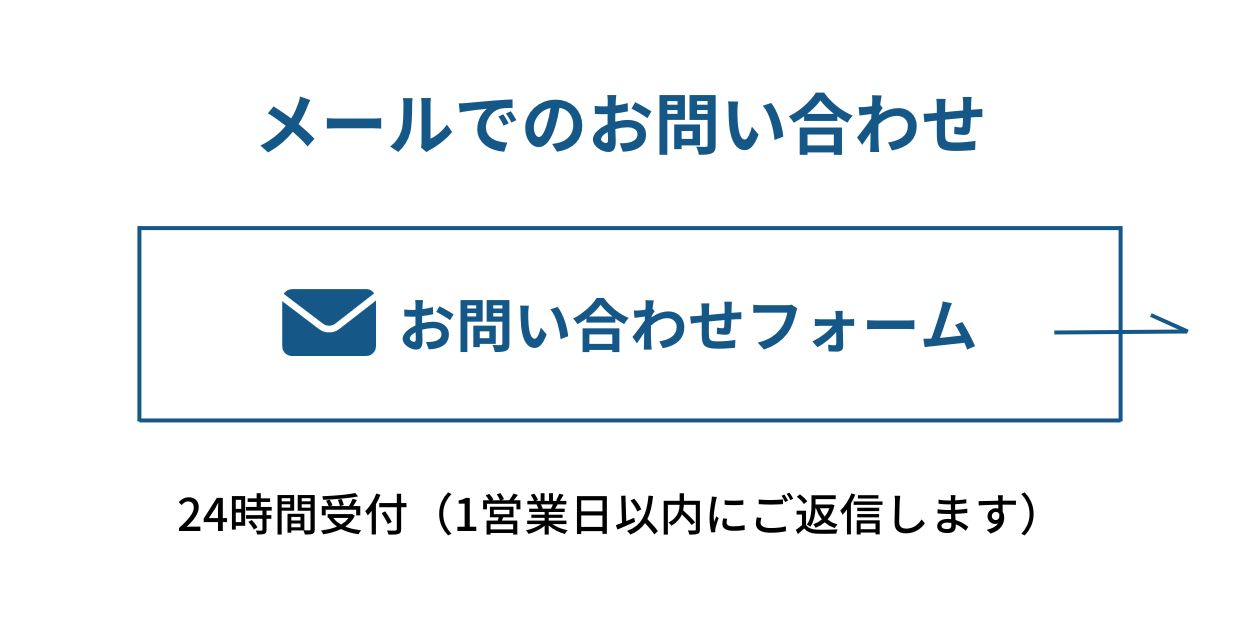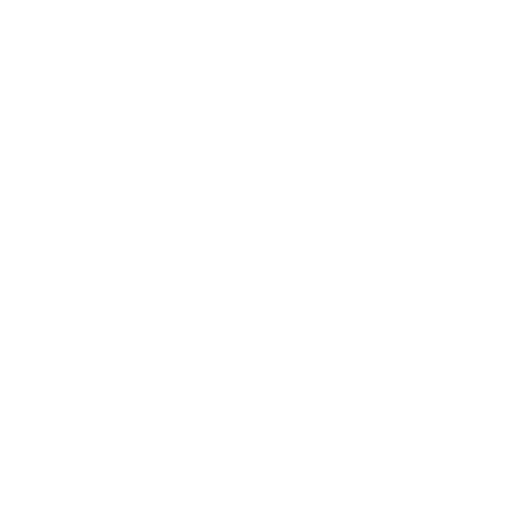- Call From Japan
- 03-5575-5583
- Email(24時間OK)
- info@tanishima.biz
告示定住 第6号「連れ子定住」
イ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
→分けて説明すると、以下の要件を満たす者が該当します。
- ①
- 日本人、永住者、特別永住者いずれかの実子であること
- ②
- 未成年かつ未婚であること
- ③
- ①の者の扶養を受けて生活すること
ロ 一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者(第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者を除く。)の扶養を受けて生活する当該者の未成年で未婚の実子
→これもわかりやすいよう要件を分けて考えます。
- ①
- 「定住者」(ただし、1年以上の在留期間を有する者)の実子であること
- ②
- 未成年かつ未婚であること
- ③
- ①の者の扶養を受けて生活すること
ハ 第三号、第四号又は前号ハに掲げる地位を有する者として上陸の許可、在留資格の変更の許可又は在留資格の取得の許可を受けた者で一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子であって素行が善良であるもの
→同様に要件を分けて整理します。
- ①
- 定住者のうち、第3号、第4号、第5号ハ(ただし、1年以上の在留期間を有する者)の実子であること
- ②
- 未成年かつ未婚であること
- ③
- ①の者の扶養を受けて生活すること
- ④
- 素行が善良であること
概ねロと同様の要件ですが、定住者である実の親が一定の場合に限り、素行善良という要件を付加しています。
ニ 日本人、永住者の在留資格をもって在留する者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の在留資格をもって在留する者の配偶者で日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって在留するものの扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子
→同様に分けて整理します。
- ①
- 実親の配偶者が日本人、永住者、特別永住者または定住者(1年以上の在留期間を持っている者に限る)であること
- ②
- 実親が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の在留資格を持つものであること
- ③
- 未成年かつ未婚であること
- ④
- ②の者の扶養を受けて生活すること
在留資格該当性、相当性
「定住者」については、他の身分系在留資格同様、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(基準省令)」の対象とならないため、上陸に際しては在留資格該当性が、変更又は更新に際してはそれに加え相当性が問題となります。
告示第6号については、イからロの全てに共通する要件として「扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子」が定められています。
このため、在留資格該当性について以下のことが主な判断材料となります。
B.活動の安定性、継続性
C.子の年齢
[1] Aについて
日本に在留するに当たり「定住者」としての活動を行うことの蓋然性として、これまで子を監護養育している実績が重要となります。
例を挙げると、一緒に暮らしていたか否か、そうでない場合は仕送りを行っていたか、親子の交流がきちんと図られてきたか、などがポイントとなります。
[2] Bについて
扶養者が子を監護養育するだけの収入、資力があるかを立証する必要があります。
[3] Cについて
明文化されてはいませんが、日本で中学校を卒業し就業が可能となる16歳頃から審査が厳しくなると言われています。そこから年齢が上がるごとに上陸許可を得ることが難しくなっていき、18歳を超えると可能性がかなり低くなると言われます。
ただし、審査要領においては「実子は、未成年(20歳未満)であれば本号に該当するので、扶養を受けないことが何らかの客観的事実に基づき明らかである場合を除き、単に20歳に近いことを理由に在留資格認定証明書交付申請を不交付とすることはしない。」と明確に書かれているので、子の年齢が高いからと言ってそれのみをもって諦めることなく、扶養を受ける蓋然性をしっかり立証することが重要であると考えます。
告示外定住ア「離婚定住」イ「死別定住」
次項では、以下をご説明いたします。